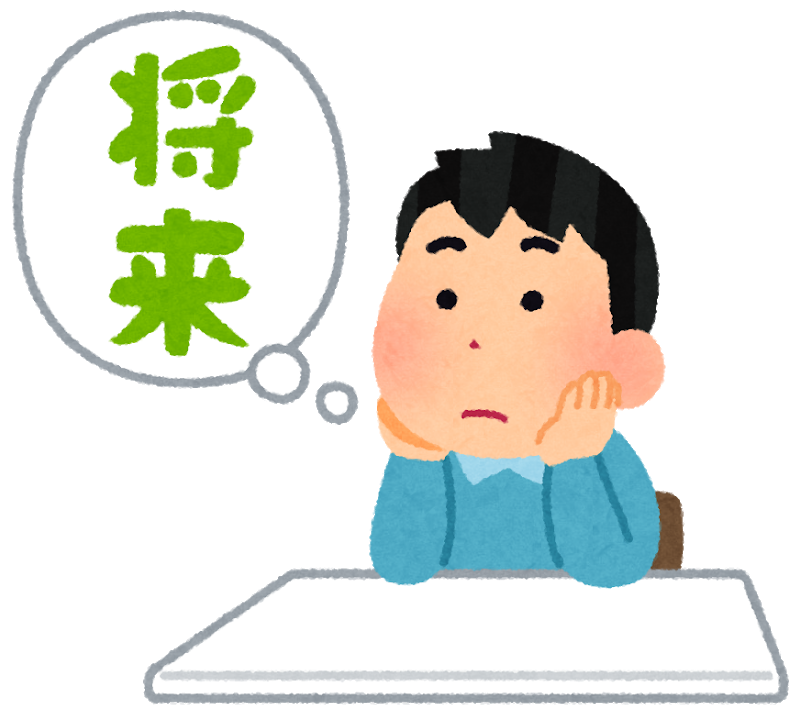人生の岐路に立たされている大学生。
「このままで本当に大丈夫なのか?」
漠然とした悩みを抱えていませんか?
就職ジャーナルでは大学1年生に対して「将来働くことについて不安はありますか」というアンケート調査を行いました。
回答は「将来が不安」と答えた人が92%。
将来について悩んでいるのはあなただけではありません。多くの大学生が将来について漠然とした不安を抱えています。
今回はそんな多くの大学生に向けて、不安の原因とその対処法について紹介します。
ぜひ最後までご覧ください。
不安になる大きな原因2つ

将来が不安になる原因は主に2つあります。
1つ目は自分に自信がないこと。
2つ目は将来の見通しが立たないことです。
自分に自信がない

自信のなさは多くの大学生が感じていることだとおもいます。
人と自分を比較して
・自分には特別な才能がない
・コミュ力がない
・学部が就職に弱い
など自分のできないことに気が向くとキリがなくなってしまい、自信がなくなってしまいます。キリがないことに漠然と悩んでいてもしかたありません。実際に行動してみましょう。
例えば、資格を取ったり、検定を受けたり、努力が目に見える目標を設定して挑戦をしてみるといいと思います。
漠然とした不安が目に見える目標に変化することで不安を解消できます。こうしてできた目標を一つ一つクリアしていくことで自信につながります。
将来の見通しが立たない

将来の見通しが立たないのも理由の一つです。
大学生の中でも明確に進路が決まっている人は少なく、多くの人が自分のやりたいことやりたい職種を探している最中になります。
やりたい職種が見つかっても、その業界に就職できるかどうかは不確定です。
不確定な未来が多く、将来の見通しが立たないと、漠然とした不安に襲われます。
そういう時は今できることに目を向けることで不安を和らげましょう。
将来の見通しが立たないのは大学生の間だけではありません。
・今の会社にいていいのだろうか?
・結婚してうまくいくだろうか?
・子供は無事に生まれてきてくれるのか?
人生において将来が確定することはなく、それに伴い不安も無限に出てきます。
今、直接不安を解消する具体的な目標を立てれないことがらも多く出てくるでしょう。
そういう時はより目先の目標を設定して、不安を和らげることに焦点を当てましょう。
先ほどの例でいくと、「自分のやりたい業種に就職できるのか」という不安から「やりたい業種に関わる資格をとる」という目標を立てます。
こうすることで、最初の不安が消えるわけではありませんが、不安を和らげることができます。
不安を無理に消そうとするのではなく共存していく考え方を身につけましょう。
不安になる要素

人生で不安になる要素はおもに2つ「仕事」と「お金」です。
人が安心して暮らすためには、お金とそれを得るための仕事に見通しがついていることが必要です。
日本FP協会が行った「人生100年時代を迎えて不安を感じること」という調査の結果、人の不安の原因は第1位が「老後の生活設計」2、3位が「自身、家族の健康」4位が「年金」についてでした。
「老後の人生設計が不安」というとわかりずらいですが、言い換えると「生涯暮らしていくうえでお金が尽きないか不安」ということです。
2,3位の健康に関しても、保険や医療費などのお金に繋がっていく不安です。
人の不安とお金、そしてそれを得るための仕事は密接につながっているのです。
ではこの2つに大学生が対処できることは何なのか。今からご紹介したいと思います。
仕事

大学生が仕事に感じている不安は以下でしょう
・自分に向いている仕事がわからない
・自分のやりたい仕事が見つからない
・仕事につくための努力の仕方がわからない
・仕事についた後、仕事ができるかわからない。
こういった不安を解決するには、今のうちから「仕事」について知識を吸収し、行動することが大切です。
仕事についての知識集めることで、今自分に足りないものがわかり、目標が立てやすくなります。
不安を目標につなげるための具体的な方法はこちらです
実際に働いているの情報を集める

実際に働いている人から話を聞いてイメージを掴みましょう。
具体的には
・自分の学部の先輩はどのような企業に就職しているのか
・自分の目指す業種に必要な資格は何なのか
・職に就いた後の勤務形態はどのようになっているのか
などです。
先輩から話を聞くことで目標を立てやすくなります。
求人をみたり、大学の就職センターに行くのもよいですが、実際に働いている社会人に話を聞くものよいと思います。
スキルアップ

知識を吸収した後は、実際にスキルアップを目指しましょう。
向上させるべきはおもに4つ
・コミュニケーション力
・経営ノウハウ
・ITリテラシー
・マーケティング
です。
1つずつ解説します。
コミュニケーション力⋯仕事で求められるコミュニケーション力とは「相手より弱い立場でありながら相手を説得する力」です。
仕事において、サークルやゼミのように対等に接する人間関係はほぼありません。利害関係が生じます。そんな中、商品をプレゼンしたり、契約を勝ち取ったりするためには「自分が弱い立場であっても相手を説得する」コミュニケーション力が必要です。
仕事におけるコミュニケーションの本なども多数発売されているので読んでみましょう。
経営ノウハウ⋯経営ノウハウとは、それぞれの企業が経営していく上での経営技術や経験を指します。企業1つ1つに独自の経営ノウハウがあり、常にアップデートされています。
学生時代から、バイト先や身近な企業の経営ノウハウを探ってみましょう。実際にお店や会社を経営している人に話を聞いてみるのも参考になりmす。
ITリテラシー⋯ITリテラシーとはITにまつわる要素を理解し操作する能力です。
officeツールなどの実際にコンピューターを直接操作する力はもちろん、SNSを活用する上でのモラルへの理解、正しい情報を探し出す力など内容は多岐にわたります。情報化社会においてこれらのスキルを上げておくことが必要です。
これらの知識は専門のWebサイト(Urey Schooなど)をみたり、資格(P検定、ITパスポート)をとったりすることで身につきます。とくに資格の会得は知識やスキルを体系的に学ぶことができるので初心者におすすめです。
マーケティング⋯マーケティングとは、商品が売れるしくみをつくるための調査や宣伝のことを指します。
マーケティングというと難しく聞こえますか、SNSなどもマーケティングの一つです。SNSで自分の売り出し方を考えてみると、マーケティングの技術が身につくだけでなく、就職活動にも役立ちます。
自分たちが普段手にする商品がどのような戦略で販売されているのか意識してみましょう。
いずれも身に着けるのは難しいですが、どれか1つでも身につけると社会で仕事をする上で、必要な人間になれます。
お金

人が暮らしていく上でお金は不可欠です。
大学生が自分の将来を考える時、「どうやって自分に必要なお金を稼ぐのか」はとても重要なポイントになります。
お金の稼ぎ方が不透明だと、金銭的なライフプランが立てられず、将来の先行きの不安につながります。
ここでは、お金の稼ぎ方を考えるポイントを紹介しますので、参考にしてみてください。
ESBI

ESBIとは、世の中にある働き方を収入の得かたで分類した概念になります。まずはESBI、それぞれの働き方の特徴を知りましょう。
働き方とその特徴を知ることで、自分が理想のライフプランを実現するための働き方がわかります是非参考にしてください。
主な特徴はこちら
E⋯Employee(労働者)企業に属しており、企業のルールがあり得られる収入に限界がある。
S⋯Self employee(自営業)自分で事業を行っている人。仕事内容、休暇、働く場所、環境はすべて自分で決める。
B⋯Business ower(ビジネスオーナー)お店やサロンのオーナーなどビジネスの権利を所有する。自動的に収入が入ってくる仕組みを持てる。
I⋯Investor(投資家)株や不動産などの権利収入がある。自動的に収入が入ってくる仕組みが作れる。
4つのうちのどれに属するかで年収が決まります。自分は年収がいくら必要なのか計算して、4つのうちどれが適切か考えましょう。
ただし、最初はE(労働者)とS(自営業)ぐらいしかなれません。ですので、この2パターンの職種の収入についてより詳しく説明します。
労働者と自営業

労働者と自営業では、収入を決めるポイントが大きく異なります。
労働者として働くなら年収は業種で決まります。自分がどのぐらいの年収が必要なのか見極めたうえで、それぞれの業種について調べましょう。
自営業として働くなら、いかに自分に価値がつけれるかで決まります。
価値を上げるには「オリジナルである」もしくは「その業界でレベルを上げる必要があります。
労働者と違い、主導権が自分にあるので具体的にどのように価値を上げるかはその人次第です。
最後に

いかがだったでしょうか。将来への不安は誰しもがいだいているものです。この記事を参考にして不安が対処できれば幸いです。
とはいえ、1人で不安を抱え込んでいても解決するのには時間がかかります。そんな人にはコワーキングスペースの利用をおすすめします。
コワーキングスペースでは各々の課題や仕事を進めるだけでなく、利用者同士で交流することができます。
特に名古屋のコワーキングスペース、コンパスルームは「生き方に悩む社会人・学生が明るく過ごせるコワーキングスペース」をテーマに営業しています。
大学生同士で交流するだけでなく、フリーランス(自営業)の人やサラリーマン(労働者)の人なども多くいるので、それぞれの働き方について生の声を知ることができます。
詳しくはこちら
気になる人はぜひ一度足を運んでみてください。